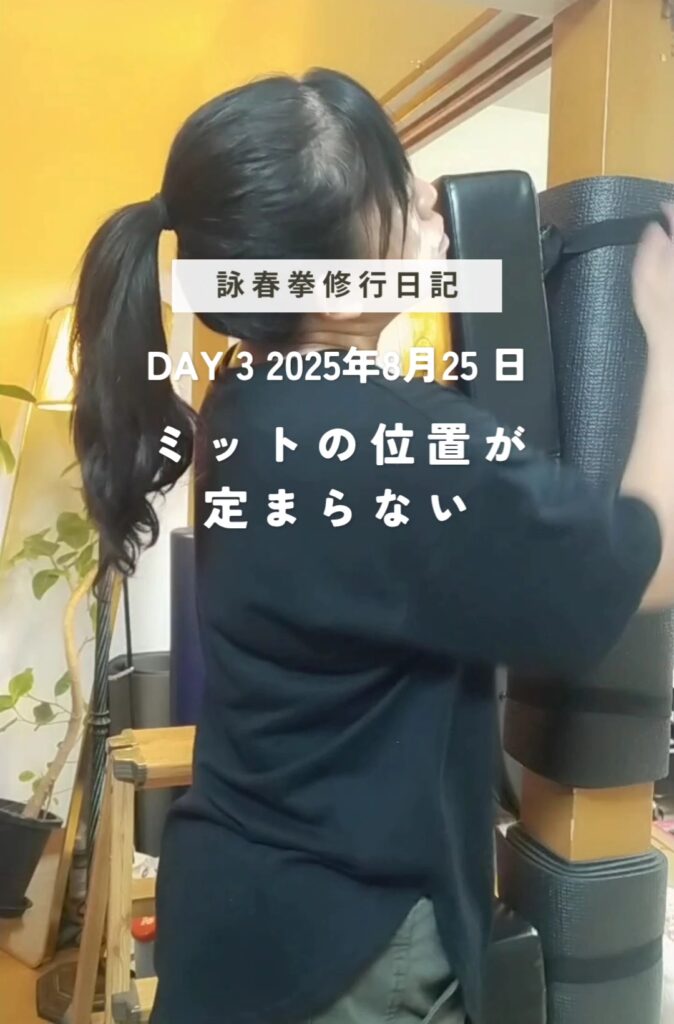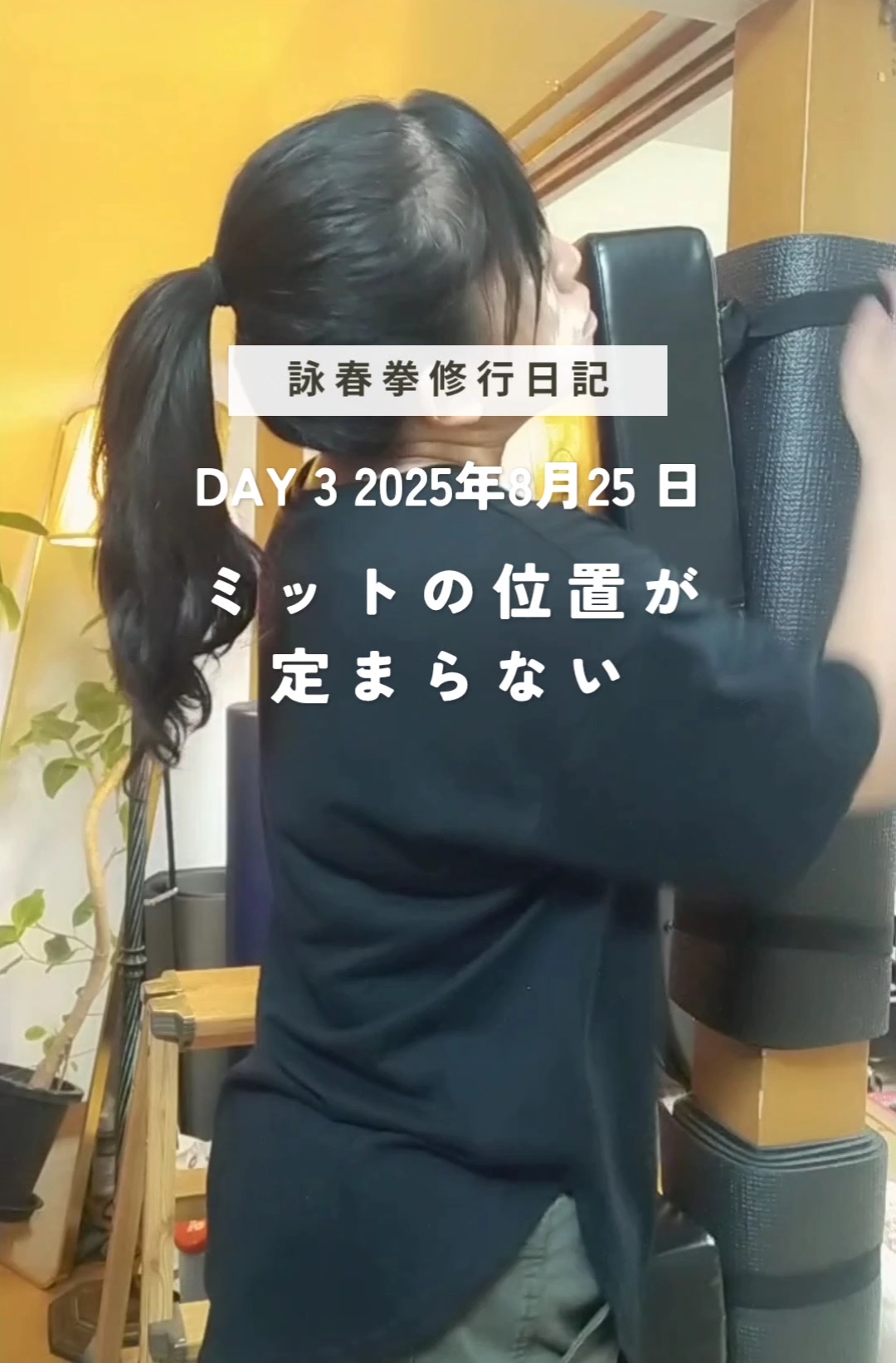私のトレーニングルームは、ちょっと変わっています。
我が家は推定築70年以上の古民家。74歳の義父が物心ついたころからあるそうで、実際は何年なのか曖昧です。
古いけれど風通しがよく、壁や床は改装しているので快適です。その一角を稽古用にアレンジして、自分だけのトレーニングルームにしました。
襖を外したあとの柱にマットをくくりつけ、それを相手に見立てて練習します。強度に不安はありつつも工夫して稽古しています。
ハイキックの練習に柱が役立つ?
この柱を使い始めたきっかけは「ハイキックの練習」でした。
稽古で課題として出されたとき、ただ「高く蹴ろう」と思ってもイメージが曖昧で、なかなか感覚が掴めませんでした。そこで柱にマットを巻きつけ、大体の目安を作って蹴るようにしたのです。
軽く当てるだけでも「これくらいの高さが必要」という感覚がつかめるので、とても役に立っています。ただし、もちろん全力で蹴ったらいつか柱が折れてしまいそう。あくまで軽めに、イメージを作るための工夫です。
ハイキックも少しづつ高くなってきましたし、今のミットの位置ではパンチには少し低い。
マットを高い位置に巻きなおしてみました。急所であるあごの位置に来るように調節して、ひとまず完成。
何日か使ってみてしっくりこないようならまた調節します。
古民家の空気と稽古の相性
古民家というと不便なことも多いのですが、実は稽古には良い面もあります。木の床は少し軋みますが、踏み込みの力が伝わりやすく、体のバランスを確認するのに役立ちます。畳の間では受け身の練習をします。
まだ全然出来ないのでゴロゴロと転がるだけになってしまっていますが、畳の程よい硬さと優しいイグサの感触が練習にちょうどいいです。
自分だけの稽古環境を持つ意味
立派な道場がなくても、工夫次第でどこでも稽古はできます。私にとってこの古民家の一角は、武術に集中できる特別な空間。何もない場所を工夫して稽古場に変えていく過程そのものが、武術を学ぶことと重なっているように感じます。
特に詠春拳は激しく移動を伴う套路がなく、技もコンパクト。畳一畳、牛が昼寝をする場所があれば稽古が出来るといわれています。それに紅船時代は足場の悪い船の上で培われてきた武術なので、そのときそのときの状態に臨機応変に対応する能力に長けていると思います。
立派な道場にもあこがれるけど、どこにいても自分の気持ち次第で稽古は出来る。
強くたくましく、どんな場所でも清らかに咲く花のように、与えられた場所で、工夫して稽古して行きたいです。
みなさんの工夫は?
今日は私の手作りトレーニングルームをご紹介しましたが、みなさんは稽古でどんな工夫をしていますか?「こんな練習道具を使っている」 「自宅ではこんな工夫をしている」など、ぜひコメントで教えてください。お互いのアイデアを共有して、より良い稽古につなげていけたら嬉しいです。