※Instagramでは簡単にご紹介しましたが、ここではもう少し掘り下げて、私がこの本から得た気づきや、日々の修行との関わりについて綴ります。
どんな本?
『 「筋肉」よりも「骨」をつかえ』は、日本古来の武術の身体操作を研究する甲野善紀さんと、「骨ストレッチ」などを考案したスポーツトレーナー松村卓さんの対談をまとめた一冊です。
対談形式で書かれているため、あたかも座談会に訪れたかのような臨場感があり、あっという間に読み進められる内容です。
筋トレで筋力を鍛えるという一般的なアプローチとは異なり、骨の動きや骨と皮膚の関係に着目した身体操作がテーマになっています。
印象に残った内容
特に印象的だったのは、「筋肉ではなく骨で動く」という発想です。
体幹を鍛えるために筋トレをするのではなく、鎖骨や肋骨の動きで体幹をつなげるという考え方は、武術で体感する骨感覚や皮膚感覚に通じるものがあります。
さらに、この本を読んで思い出したのが、子供の頃に腕を骨折したときのエピソードです。
当時、お医者さんに「骨には神経がないのに、なぜこんなに痛いの?」と質問したことがありました。
そのときのお医者さんはとても優しく、「骨そのものではなく『骨膜』に沢山の神経があり、その骨膜が刺激を感じている」と教えてくれました。
その言葉が強く印象に残っており、この本を読んで再びその記憶が蘇りました。
読後の感想
本書を読み進める中で感じたのは、「骨を動かすものは何か?」という問いです。
人の体が動くメカニズムを考えれば、それは単に筋肉の収縮や関節の動きだけではなく、神経の伝達と脳の信号処理が大きく関わっています。
「皮膚に気づかれずに骨に伝える」 「脳が錯覚する」 「骨から動く」という感覚は、普段の稽古でも重要な要素であり、こうした感覚が鍛えられることで接触面の感覚が薄れるように感じます。
このように、骨を感じることは、武術だけでなく、日常の身体感覚を深めるためにも非常に重要だと感じさせられる一冊でした。
この本はこんな方におすすめ!
- 武術や身体操作に興味がある方
- 筋肉だけでなく骨の動きに注目したい方
- 身体感覚や意識の使い方を探求している方
ご紹介した書籍はこちら
骨感覚や身体操作に興味のある方におすすめの一冊。武術の達人とスポーツトレーナーの対談から、骨の動きと意識の使い方を学べます。
📝 関連記事
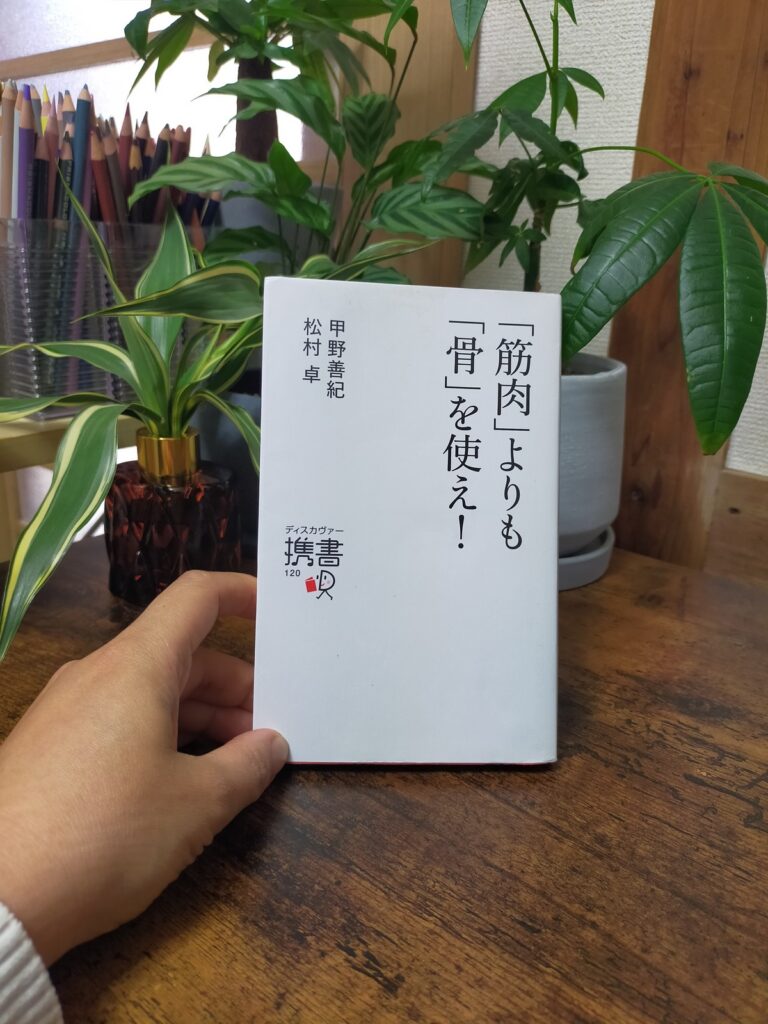

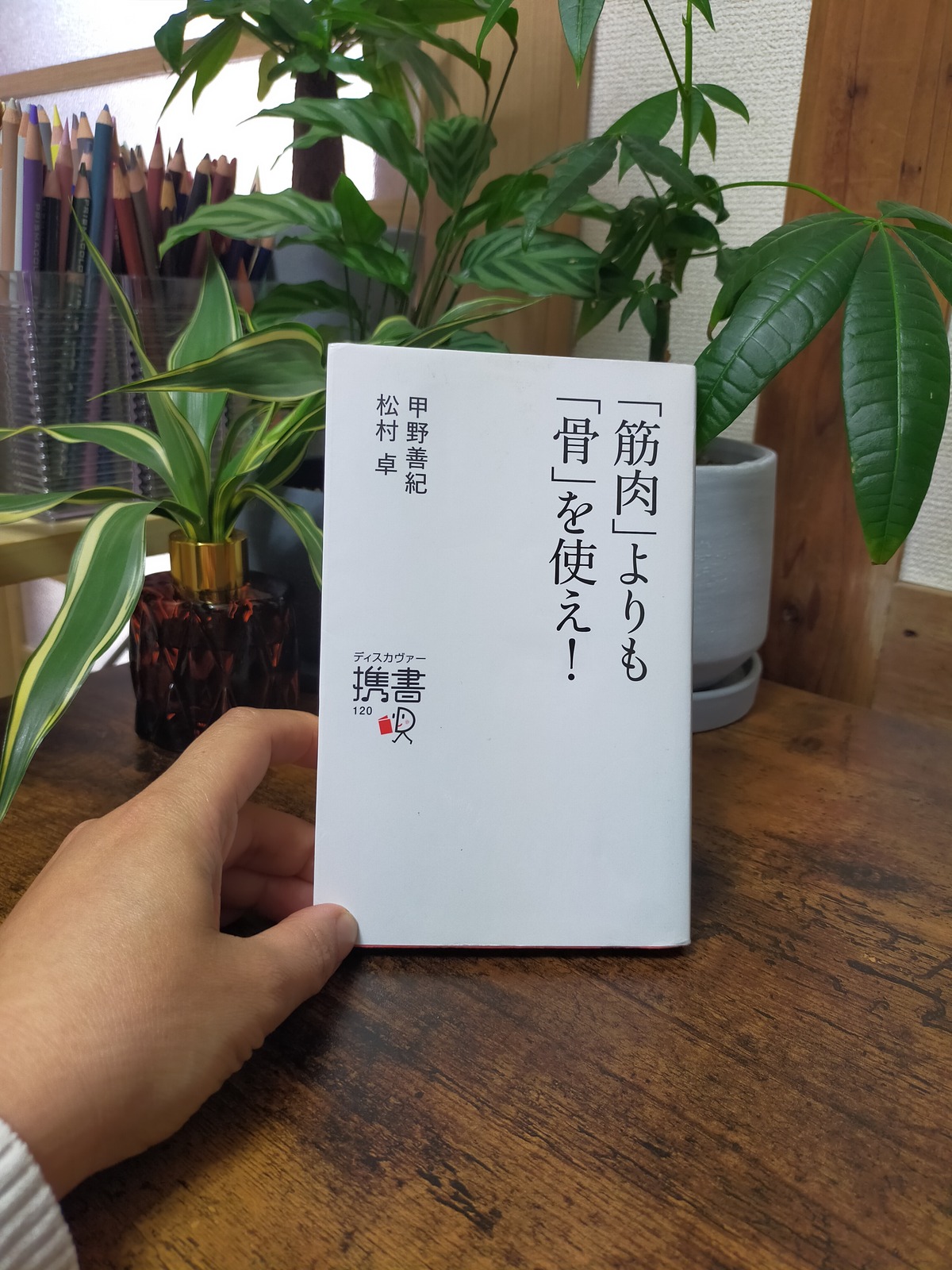
久々のコメントです。
甲野先生、とても素晴らしい武術家の方ですよね。動きの意味するものは何か、そこからどうしていくのか等々とても感銘を受けます。
『骨を使う』は黒帯ワールドで中達也師範も言ってはりましたね。『コツを掴む』のコツ=骨やと。武道やスタイルは違えど、突き詰めていけばつながることも多いんやと思いました。
私も未熟ながらErinaさんを見習い研究研鑽に努めていきますね!
コツ=骨は中達也師範も仰られてたんですね!言葉もすんなりと入ってきますし、なるほどなぁと思うことが多い本でした。強い!と思える方は共通点も多く、本当に突き詰めた先は繋がっているのではないかと思えます。日本舞踊をするようになってからは、日本古来の体の使い方にも詠春拳との共通点を感じるようになりましたし、武芸も繋がっているんだなぁと思いました。見習うだなんて、まだまだ未熟者でございます~。ふるちゃんさんの方が大先輩ですのに、いつもお優しいお言葉有難うございます。